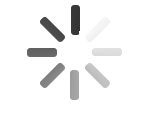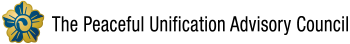[海外] 日本地域会議、「転換期の東アジアの平和の模索」、韓中日平和フォーラム開催
- 日本地域会議
- 2020-10-27 ~ 2020-10-27
日本地域会議、「転換期の東アジアの平和の模索」、韓中日平和フォーラム開催
民主平和統一諮問会議は日本地域会議(副議長:キム・グァンイル)の主管で、10月27日、ソウル新羅ホテル迎賓館にて韓国、中国、日本の専門家を招待した中、「韓・中・日の平和フォーラム」を開催した。

フォーラムには韓・中・日の韓半島専門家8人が参加し、新型コロナファンデミク、アメリカ大統領選挙など転換期の北東アジア情勢を診断し、韓半島の平和共同体・生命共同体の形成のための3カ国協力方略などについて議論した。特に中国と日本の専門家らはオンラインで最後まで参加した。



開会式には民主平和統一諮問会議のチョン・セヒョン首席副議長、国会外交統一委員会ソン・ヨンギル委員長、パク・ジン議員などの韓国側の主要関係者、そして富田浩司駐大韓民国日本国大使館特命全権大使、シン・ハイミング駐大韓民国中華人民共和国特命全権大使が参加し、様々なメッセージを伝えた。
まず、キム・グァンイル日本副議長は開会の辞で、「世界3大経済圏の力を持つ東アジアの中心国家である韓・中・日3国は過去の歴史のしがらみによる葛藤と反目が積もっていく一方だ」とし、「これは人類共同体の繁栄と生存を妨げる問題であり、韓・中・日はこれを解決するために団結と協力の礎を築かなければならない」と強調した。
チョン・セヒョン首席副議長は歓迎の辞、「新型コロナの対処に模範を示している韓・中・日3カ国の成功事例をもとに、北東アジアの防疫・保健分野の協力を拡大していければ、韓半島と北東アジアの平和秩序において明るい変化を引き起こすことができる」と述べた。
今回の行事を総括したイ・スンファン事務局長は、「2018年の平昌冬季オリンピックから始まった北東アジアの平和オリンピックの流れが、2021年の東京と2022年の北京を経て「2032年間ソウル・平壌共同オリンピック」へとつながることを期待している」とし、挨拶を締めくくった。


<ソン・ヨンギル国会外交統一委員長、パク・ジン国会議員>
祝辞でソン・ヨンギル国会外交統一委員長は、「議会外交を通じて、中国・日本との対話を試みながら緊密に協力していくことや、必要な政策と立法などを通じて、韓半島の平和構築への偉大な道のりに共にしていきたい」と述べた。
パク・ジン国会議員は、「北朝鮮の非核化だけが韓半島と北東アジアの真の平和へ導くことができるという事実を念頭におき、韓・中・日3か国の平和・繁栄を目指して心を一つに結集することを願うととともに、特に非核化のない終戦宣言はむしろ韓半島の安保をより危険にさらしてしまうという点も深く認識しなければならない」と強調した。


<富田浩司駐韓日本大使、シン・ハイミング駐韓中国大使
富田浩司駐大韓民国日本国大使は、「2018年以降、平昌、東京、北京オリンピック・パラリンピックというスポーツの祭典がアジアで連続開催され、これを機に三カ国間の人的交流が活発になると期待している」と述べた。
シン・ハイミング駐大韓民国中華人民共和国大使は、「我々は平和、発展、協力、共生という時代の流れに合わせて、戦略的には信頼と協力、経済的にはwin-win、安全保障的には恒久的な平和の関係が築かれるように北東アジアの環境を整っていかねばならない」と述べた。

次はムン・ジョンイン大統領統一外交安保特別補佐官が「コロナ以降の世界秩序と転換期の東アジア」をテーマに基調講演を行った。
ムン・ジョンイン特別補佐官は東アジアについて、「悪化した関係の現状維持と新しい冷戦の到来」といった災いを避けるためには、韓・中・日の政治指導者が会って、米・中対立の悪化の解決策を模索し、市民社会の国境を超えるネットワークを活性化しながら、 災いが起こることを防がなければならないと強調した。
そして「韓半島の平和は東アジアの平和につながるオーソドックスな経路だ」としたうえで、、「韓半島の非核化と平和体制を同時に推進しなければならず、そのスタートラインは「終戦宣言」になるだろう」と述べた。また、「終戦宣言を「口火」に非核化を推進し、平和体制を作る過程において、私たちはその中心的な役割を果たさねばならない」と強調した。

問題提起とディスカッションはキム・ギジョン延世大教授の司会で、韓・中・日の専門家が1人ずつ問題提起をした後、議論を形で行われた。
まず、コ・ユファン統一研究院長が「韓半島の平和プロセスと東アジアの平和のための韓・中・日の協力」をテーマに発表した。コ・ユファン院長は「トップダウン方式では中国や日本の役割の比重が大きくなかったが、平和・非核化の交換交渉が本格化すれば、中国や日本の役割の割合が高くなる」との見通しを示した。
そして、「新型コロナのファンデミク宣言が出された中で、域内の国同士が本腰を入れて協力をしていくためには、最近、ムン・ジェイン大統領が国連演説で提案した、北東アジア防疫・保健協力体の実現に向けた韓・中・日の積極的な協力体制づくりを急がなければならない」とした。つまり、感染症対策のための国境地域における共同防疫など、「サブ政治」の領域における国家間の協力とこれを通じた政治的信頼の形成を強調した。

次に、ワン・イージョウ北京大学教授は「不確実な時代における北東アジアの安保」について発表した。ワン・イージョウ教授は北東アジア地域の未来について、「北東アジア地域は、新型コロナファンデミクの陰から脱し、次の発展段階へ進んでいくのに比較的有利な状況にあり、これは協力的な安全保障と地域の安定を支える強固な基盤になる」と述べた。
北東アジア安保のジレンマを解決するためには、「フランス・ドイツ、マレーシア・シンガポールのように、長い間敵対関係にあった国同士の歴史的和解の事例(すなわち、機能主義と新機能主義理論を効果的に示す事例)を参照し、地域の状況に合わせて将来を設計しながら、より大きな誇りを持つことも忘れてはならない」と強調した。

最後に問題提起をした添谷芳秀慶応大名誉教授は、「韓・中・日協力の展望」をテーマに発表した。添谷教授は東アジアの状況について、「韓・中・日3か国は、現在急速に強くなった中国を中心軸に秩序が再編されている」と診断したうえで、「米・中関係に韓国と日本がどのように協力するかによって冷え込んでいる両国の対立を緩和することができる」と述べた。
続いて、「韓国は分断前の本来の姿を追求し、中国の国力は高まるばかりで、日本は衰退している」とし、「このような状況の中で最も重要なのはコンセンサスの形成であり、そのためには相手が「なぜそう思うのか」について熟考する姿勢が根底になければならない」と締めくくった。
問題提起に続くディスカッションでは、3人の専門家が参加した。
まず、イ・ヒオク成均館大教授は、「アメリカ大統領選挙の後、アメリカの外交政策に変化があっても、米・中関係の問題においては、「対立の中での協力」が維持される可能性が高い」との展望を示し、「日本がパワーバランスを求める過程で、東アジアの連帯と共生より、アメリカ寄りに傾き、中国を牽制しつつ近づこうとしているという評判を克服しなければならない」と述べた。
そして、韓・中・日首脳会談の定例化などの対話を強調しながら、「東アジア側の信頼構築と主権の尊重は共同体への近道だ」とした。さらに、「東アジアの平和のためには域内の他の国を自然排除する同盟、軍事戦略、地域戦略については慎重でなければならない」と訴えた。
続いてヤン・ギホ聖公会大教授は、「韓日両国はパートナーシップを強化しつつ、北東アジアの平和や繁栄の安定版にならなければならないと述べた添谷名誉教授の意見に共感する」とし、「新型コロナという重大な懸案をはじめ、福島原発の汚染水放出の問題、徴用工問題などの解決策を見出せるように、政治的リーダーシップを発揮しなければならず、早いうちに韓日首脳会談が開かれることを願う」と話した。
最後の発表者である堀山明子毎日新聞ソウル支局特派員は、来年予定の東京オリンピックを機に予想される日朝協議と韓半島の平和プロセスの進展の可能性について論じながら、東京オリンピックが2021年に開催される前提の下、関係国の平和シナリオへのオーダーを要請した。
堀山明子支局長は、「現在菅首相は無条件での対話と条件のない訪朝の意思を表明しており、北朝鮮高官の来日が実現すれば、2018年の平昌に次ぐ平和オリンピックリレーが続くことになる」としながらも、「実際の成功の可否は、アメリカ大統領選挙後の米朝関係にかかっている」との見通しを述べて議論を締めくくった。

-
ご覧になった情報に満足ですか?